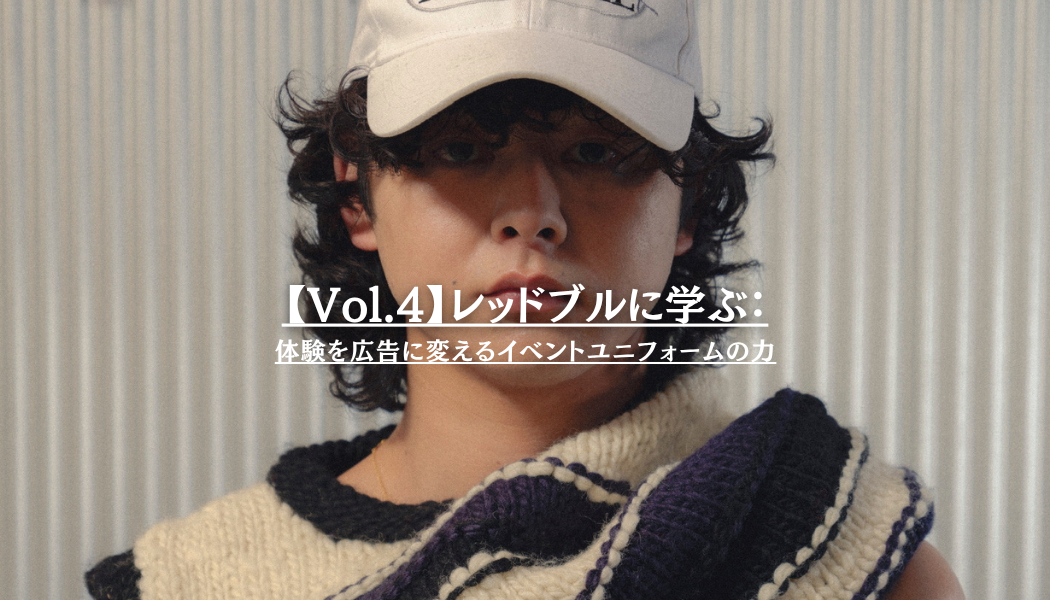「服が語るブランド体験」を極限まで突き詰めている企業がある。
それが、Red Bull(レッドブル)だ。
同社が世界各地で開催する「Red Bull Flugtag(フルークタグ)」や「Crashed Ice」などのイベントは、競技のスリルとユニフォームの一体感で人々の記憶に残る。
ここでは、Flugtag(空飛ぶ日)を例に、短期間で最大の印象を残すユニフォーム設計の秘密を探る。
Red Bull Flugtagとは
Flugtagはドイツ語で「飛行の日」を意味し、参加者が自作の“飛行機”で海や川に飛び出すユニークな競技イベントだ。
1980年代後半にオーストリア・ウィーンで始まり、いまでは世界数十都市で開催されている。
日本でも東京・大阪などで開催され、数万人規模の観客を集める。
公式ページ:Red Bull Flugtag | redbull.com
競技の目的は「誰が一番遠くまで飛べるか」ではなく、“誰が一番創造的に飛ぶか”。
そのため、コスチュームやデザイン性が重要な評価要素となっている。
安全とデザインの両立
イベントルールでは、すべての参加者にヘルメットとライフジャケットの着用が義務付けられている。
これらは安全のための装備であると同時に、ブランドカラー(赤・青・銀)で統一されたデザインが採用されている。
公式ルール:Red Bull Flugtag Rules | redbull.com
つまり、機能性とデザイン性を両立させることで、「安全装備=レッドブルらしい記号」として成立している。
ライフジャケットやスタッフウェア、メカニック用ベストに至るまで、一貫した配色とロゴ配置によって視覚的な統一感を生んでいる。
「体験そのものを広告化」する仕組み
1. 参加者がブランドの一部になる
参加チームは自らの衣装を制作し、その過程をSNSで発信する。
準備段階からイベント当日まで、参加者自身が“動く広告塔”となる。
2. 安全装備がフォトジェニック
ライフジャケットやヘルメットは視認性の高い色で統一され、メディア映像で強い印象を残す。
安全性の象徴が、同時に“ブランドの色”としても記憶に刻まれる。
3. 統一感と個性の共存
運営スタッフ・審査員・参加者が同系統の配色を用いることで、会場全体に「ブランド空間」としての一体感が生まれる。
一方で、チーム衣装の自由度を保つことで多様性と創造性も両立している。
記憶に残る理由
- ・非日常性の演出
日常では見られない奇抜な衣装と、空中を舞うパフォーマンス。これが観客の五感に強く残る。 - ・安全性と遊び心の融合
「危険そうで安全」という矛盾が、イベントの魅力を高めている。 - ・撮影されることを前提にした設計
背面・肩・ヘルメットに配置されたロゴは、ドローン撮影でも明瞭に認識できる。
“映える構造”がSNS拡散の起点になっている。
他イベントへの応用ポイント
- ・安全基準をデザインに昇華させる
反射材やプロテクターを「必要だから付ける」のではなく、「デザイン要素として見せる」。 - ・撮影環境を最初に想定する
スマートフォンやドローンでの被写体を想定し、背面ロゴ・肩位置を設計段階でシミュレーション。 - ・チームとスタッフの色統一
運営者と参加者のウェアを同一カラートーンで揃えることで、写真・動画の統一感を演出。 - ・短期イベントでも“ブランド記号”を固定化
1回限りの開催であっても、色・ロゴ配置・素材感を毎回継続することで「〇〇=この色」という記憶を植え付ける。
KPI設計
| 分類 | 測定指標 |
|---|---|
| UGC効果 | #イベント名 の投稿数、動画再生数、リーチ |
| 報道露出 | メディア掲載件数、使用写真点数、映像露出秒数 |
| 安全性 | 事故ゼロ達成率、軽傷発生率の推移 |
| ブランド想起 | イベント後の認知度・好感度調査 |
デザインチェックリスト
- ・色:ブランドカラーを中心に構成(赤・青・銀)
- ・素材:耐水・速乾・軽量性・防汚加工
- ・ロゴ配置:背面ヨーク、胸、ヘルメット側面に水平配置
- ・安全装備:反射材ラインで意匠性を強化
- ・撮影対応:ドローン俯瞰や動画でも識別しやすい面積設計
実務的な工夫
- ・レンタルと再整備
ライフジャケットやヘルメットを共通化し、再利用することで環境負荷とコストを削減。・ - ・安全動画の共有
装着方法や立ち入り禁止エリアを動画で共有し、当日の混乱を防止。 - ・スポンサー露出の最適化
カメラに最も写りやすい「肩・背中・腕」に協賛ロゴを配置。過剰な装飾は避け、上品な露出バランスを保つ。
まとめ
レッドブルのイベントユニフォームは、「安全規定をブランド体験に転換した成功例」である。
安全の象徴である装具が、デザインと結びついた瞬間、それは単なる備品ではなく「記号」となる。
参加者が誇りを持って身につけ、観客が写真を撮りたくなる――その仕組みを徹底して設計している。
イベントユニフォームの未来は、もはや“裏方の服”ではない。
着ること自体が広告になる時代、服は体験そのものを拡張するメディアなのだ。参加者が誇りを持ち、観客が撮りたくなる服を設計すれば、ブランドの記憶は長く残る。
服が人を動かし、人がブランドを語る――これが現代のユニフォームデザインの到達点だ。