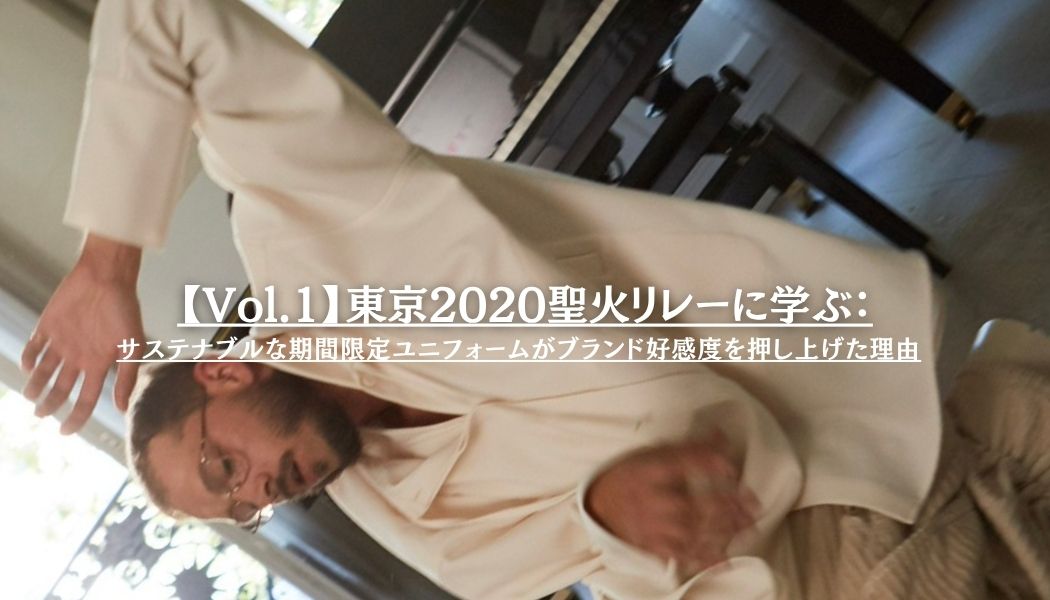要約
イベントやキャンペーンで“その時だけ”着用されるユニフォームは、単なる衣装ではありません。正しく設計すれば、来場者の記憶に刺さり、SNSで拡散され、ブランドが伝えたい価値(環境配慮、革新性、ホスピタリティ等)を分かりやすく可視化します。本稿では東京2020の聖火リレーで採用されたリサイクル素材のユニフォームを例に、短期ユニフォームの戦略設計とKPIの作り方を解説します。
事例:コカ・コーラ×東京2020 聖火リレー・ユニフォーム
東京2020の聖火リレーでは、コカ・コーラが回収したPETボトルを再生して作られたユニフォームが採用されました。国際オリンピック委員会の公式発表でも、リサイクルボトル由来の素材が使われたことが明記されています。これにより“持続可能性への姿勢”を視覚言語として示し、イベントの主役である聖火の“つなぐ”という物語と、循環の思想を重ね合わせることに成功しました。 オリンピック公式サイト
また、聖火リレーは全国121日間にわたる移動型イベントであり、統一デザインのユニフォームは沿道での視認性を高める“動くサイン”として機能。メディア露出が積み重なるたびに、白を基調としたクリーンな印象とサステナブル素材という二つの記号が反復され、ブランド想起が強化されました。 オリンピック公式サイト
同時期にコカ・コーラ日本は東京2020に向けた社内横断プロジェクト「Team Coca-Cola」を組成し、ユニフォームやプロモーションの設計思想を“ブランド体験の一貫性”という軸で束ねています。制服はその“最前線の媒体”として扱われ、他タッチポイントとの視覚統合(赤・白の配色、ロゴのサイズ/位置、写真映え)を徹底しました。 コカ・コーラ
どこが優れていたか
- ・メッセージの一刀両断化:素材=循環の物語。長い説明を要さず、着た瞬間に意味が伝わる。
- ・反復露出の設計:121日×全国=写真・動画の再生産。映像ニュースやSNSのサムネでも識別できる“白+赤”の強さ。 オリンピック公式サイト
- ・ユニフォームを媒体として捉えた:告知物・トラック・バナー・グッズと統一。“人が動く媒体”は接触頻度が高い。 コカ・コーラ
WANSIE UNIFORMならどう応用するか
- ・素材で語る:再生ポリエステルや工場端材のアップサイクル、植物由来ボタン等、“ひと目で価値がわかる部材”を先に決める。
- ・露出計画から逆算:フォトコール、メディア動線、ボランティアの立ち位置をプロットし、写真に写る面積からロゴ比率・アクセントカラーを決定。
- ・“持ち帰り”を設計:使用後に来場者やスタッフが記念として残したくなる仕掛け(ネームタグ、日付刺繍、地域限定配色)を入れる。
KPI設計
- ・視認KPI:メディア露出件数、SNSでの写真投稿数/ハッシュタグ言及数、アーンドリーチ(推定)。
- ・想起KPI:イベント終了後の**ブランド想起率(認知・好意・推奨意向)**の事後アンケート。
- ・循環KPI:使用後の二次利用率(スタッフの私用継続率、寄付・回収率)。
- ・コストKPI:一点あたり製造原価×露出回数=CPM換算での費用対効果。
クリエイティブ仕様の指針
- ・色:イベントのキービジュアル→会場サイン→ユニフォームへ等色。
- ・シルエット:立位/歩行/整列の三態で最も整って見える“準フォーマル”を軸に。
- ・素材:光の乱反射を抑えるセミマット。屋外・夜間照明下の白飛び対策。
- ・ディテール:撮影時に“胸ポケットが水平に見える”ステッチ線、名札の位置統一。
- ・サイズ:ボランティア中心の場合はジェンダーニュートラルなサイズグレーディング。
- ・ガーメントケア:輸送時の折りジワ回復性(ポリエステル混紡比率と防シワ加工)。
導入時の予算感(目安)
- 100〜500着:プリント主体で¥6,000〜¥12,000/着(再生ポリ混、夜間反射タブ付)。
- 500〜2,000着:型紙共通化+一部別注で¥5,000〜¥9,000/着。
- 2,000着以上:生地先上げ+量産で¥4,000〜¥7,000/着。
※仕様・時期・原材料市況で変動。まずは最小ロット試作→露出テスト→本番を推奨。
制作スケジュール例
- ・企画・要件定義(2週):テーマ、KPI、露出計画の合意。
- ・デザイン&試作(3〜4週):試着会、写真テスト(屋外/夜間)。
- ・量産(4〜8週):工場キャパにより変動。東アジア生産も可。
- ・納品・運用(1〜2週):サイズ配布計画、現場更衣オペの指導。
よくある失敗と回避
- ・白Tが透ける問題:番手と密度、インナー指定で回避。
- ・ロゴが歪む:胸のダーツ位置とシルク版の当て方を事前検証。
- ・サイズ切れ:役割別に必要サイズをヒートマップで見える化。