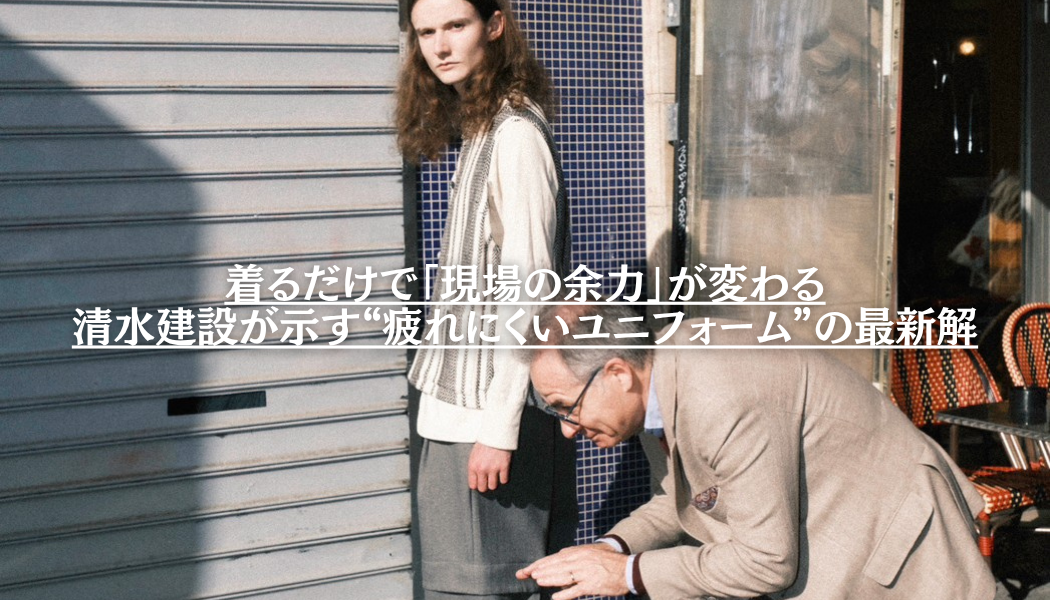建設現場は、長時間の立ち作業・屈伸・運搬・気温変化が連続する「体力の削れやすい環境」。その前提に対し、清水建設は社内アンケートと従業員投票を起点に、機能素材・立体裁断を取り入れた作業用ユニフォームの全面リニューアルを断行しました(2024年11月着用開始)。さらに“空調服”の早期導入(2016)や、旧ユニフォームを土壌改良材に再資源化(2025)する取り組みまで含め、「疲労低減×安全×環境」の三位一体を推し進めています。本稿は清水建設の公式発表に基づく事実と、そこで読み取れる“疲れにくいユニフォーム設計”の原則を、ユニフォーム発注の実務に落として解説します。
(参照サイト:Shimz+2Shimz+2)
1|清水建設の“全面リニューアル”が示す方向性
- 背景とプロセス:導入33年超の現行ユニフォームに対し、全社アンケート→課題抽出→複数案作成→従業員投票で最終決定。伸縮性・フィット性・吸水速乾・通気などの機能要件を強化。2024年11月より順次着用開始。デザインは性別・年齢を超えて受け入れやすいシンプル&スマート路線。 (参照サイト:Shimz)
- 示唆:現場当事者の声を起点に“合意形成”している点が要。トップダウンの押し付けではなく、現場可用性からの最適解を採っている。
1.1 “疲れにくい”につながる仕様のキー
- 軽量×ストレッチ:反復動作での筋持久コストを削減。
- 吸汗速乾×通気:深部体温の上昇抑制に寄与し、午後の認知・判断の落ち込みを緩和。
- 立体裁断:しゃがみ・ひねり・高所作業の関節可動域を確保。
これらは清水建設が掲げる改善ポイントと合致します。 (参照サイト:Shimz)
2|“空調服”の早期導入(2016)という先行事例
炎天下対策として小型電動ファンで外気を取り込み、気化熱で身体を冷やすジャケット(空調服)を現場ユニフォームに合わせて導入(2016発表)。ヘルメットの軽量化(450g→350g)と合わせ、熱中症リスク低減の実装を前倒ししてきた実績があります。 (参照サイト:Shimz)
参考:空調服の一般的な仕組み(外気を取り込み汗の気化熱で冷却)
※清水建設の固有仕様ではなく、市場の一般的技術解説として。 (参照サイト:sunco.co.jp)
3|“使い終わった後”までがユニフォーム設計
2025年には旧ユニフォーム約14万着(約60t)を回収し、土壌改良材に再資源化。焼却比でCO₂を約80%削減する見込みで、以降も毎年約3万着の継続回収を計画。**「導入→運用→回収→再資源化」**というライフサイクルで設計を完結させています。 (参照サイト:Shimz+1)
4|“疲れにくいユニフォーム”の実務設計テンプレ
現場要件は違っても、疲労の源は共通です。WANSIE UNIFORMでの実装例として、以下を推奨します。
姿勢・動作ベースのパターン設計
- ・しゃがみやすい股上・股下の可動域、腕上げ時に裾が出にくい袖ぐりの回転。
- ・重量分散:ツールポケットは左右バランス+肩への荷重逃がし。
マテリアル設計
- ・二重目的の混率(例:ポリ×綿×PU)で伸び・戻り・耐摩耗をバランス取り。
- ・吸汗速乾×通気+防汚・防シワで、見た目の清潔さ=信頼を維持。
熱負荷対策
- ・ベンチレーション(背ヨーク・脇下メッシュ)/色設計(直射での温度上昇抑制)。
- ・空調服デバイス互換のスペースや配線通路を確保。
視認性×安全
- ・反射トリムの幅・位置を“動線上で見える角度”に。
- ・高所・夜間を想定した配色コントラスト。
メンテナンス性/TCO
- ・産業用洗濯でも収縮・退色・プリント剥離が起きにくい仕様。
- ・回収・再資源化オプションまで設計し、**調達部門のKPI(CO₂/廃棄コスト)**に連結。
5|市場背景:猛暑対策ウェアの標準化とブランド例
日本の作業現場では、ファン付きウェア(通称“空調服”)が広く普及。代表的メーカーの一つにBURTLE(バートル)があり、「AIRCRAFT(エアークラフト)」シリーズ等で高風量・24Vバッテリー等のプロダクトを展開しています(※本稿は“市場例”としての紹介で、清水建設との関係性を示すものではありません)。 (参照サイト:BURTLE+1)
6|KPI:ユニフォームで“疲れ”を可視化する
- ・身体負担:心拍数の平均推移、午後の歩容・姿勢崩れ率、ピッキングなど反復動作の1サイクル時間。
- ・熱負荷:WBGT・深部体温推定・水分補給回数。
- ・安全:つまづき・接触のヒヤリハット報告件数、夜間の視認に関する指摘減少。
- ・TCO/環境:洗濯回数あたりの外観維持点数、回収率、再資源化率・CO₂削減量。
清水建設の一連の発表は、“疲れにくさ”を設備・運用・環境まで拡張した経営KPIの組み立てを示唆しています。 (参照サイト:Shimz+1)
7|失敗しない導入プロセス(発注の実務)
- ・現場ヒアリング→要件化(動作、気候、安全規格、メンテ頻度)。
- ・一次試作→“動きの試着会”(屈伸・昇降・搬送・高所動作を動画で評価)。
- ・小ロット先行投入→KPI計測(夏季・夜間での疲労プロファイルを比較)。
- ・改善反映→本生産(サイズ曲線、役割別仕様、洗濯耐性の規格入れ)。
- ・回収・再資源化スキーム設計(社内広報で“脱・使い捨て”を宣言)。
8|まとめ——“服は設備”である
清水建設の事例は、ユニフォームを“コストの服”から“設備=投資”へ引き上げたことに本質があります。
- ・現場の声を起点とした機能×意匠の更新(2024)。
- ・暑熱対策のデバイス連携を早期に取り入れる実装力(2016)。
- ・回収→再資源化まで設計した循環志向(2025)。
この一連の動きは、疲労低減・事故予防・採用/広報価値・環境KPIを同時に押し上げる、これからの“疲れにくいユニフォーム”の教科書と言えます。(参照サイト: Shimz+2Shimz+2)
お問い合わせ(CTA)
WANSIE UNIFORMでは、小ロットの先行テスト→本番量産→回収・再資源化オプションまで一気通貫で設計可能です。
現場の“疲れ”を、服から変えませんか。KPI設計から伴走します。